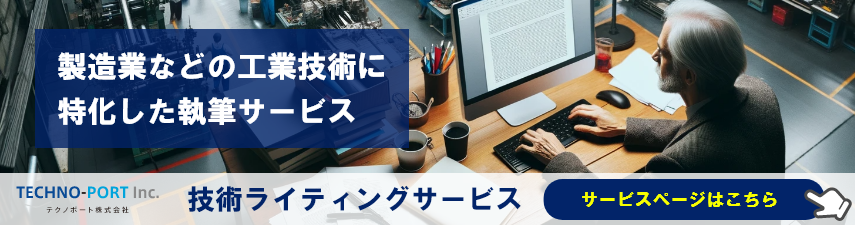こんにちは、テクノポートの五月女です。製造業のメーカーは、自社製品の使い方や操作方法を解説する取扱説明書を提供することが多くなっています。近年、従来の紙やPDFの取扱説明書だけでは伝わりにくい部分を、動画によって直感的に伝えることが多くなっています。
本記事では、製造業メーカーが動画マニュアルを提供すべき理由や、その活用方法・作成方法について詳しく解説します。
この記事の目次
紙・PDF説明書の限界と顧客の課題
「動き」や「音」、「工具の角度」など動的情報が伝わりにくい
静止画や文章だけでは、複雑な操作の動作や音のニュアンス、工具の正しい角度といった 動的な要素を十分に表現できません。その結果、ユーザーは実際の作業イメージを掴みにくくなります。
必要な情報にたどり着きにくいが伝わりにくい
分厚いマニュアルは敬遠されがちで、困った際は営業担当に連絡するケースが多くなっています。その結果、営業が説明のために訪問したり、WEB会議で説明すると言ったことに時間を割くことが多くなっています。
誤操作による事故・故障・返品のリスク
マニュアルを十分に読まなかったり内容を誤解したりすると、誤った使い方による 製品事故が発生する可能性があります。事前に注意喚起や正しい操作を伝えていないと、事故や故障につながり、最悪の場合メーカーに損害賠償などの責任が及ぶケースも報告されています。
多言語対応が難しく、表現の誤解が発生
製品を海外展開する際、取説を複数言語に翻訳するには莫大なコストと手間がかかります。しかも翻訳の際に専門用語のニュアンス違いや表現の誤解が生じる恐れがあり、文化や言語の差によるミスコミュニケーションにつながりかねません。
動画マニュアル事例
こうした課題に対応するため、既に 複数の製造業メーカーが動画マニュアルや製品動画の提供を開始しています。以下では、その具体的な事例を紹介します。
田中科学機器製作株式会社
引火点試験器などを製造する田中科学機器製作株式会社では、自社試験機ごとの紹介動画をYouTube公式チャンネルで公開しています。ユーザーは動画で実際の試験機の操作イメージをつかむことができ、マニュアルでは伝わりにくい操作手順や動作音も確認できます。
例えば引火点測定器の動画では、点火から測定までの流れを映像で示し、複雑な試験手順を直感的に理解できるよう工夫されています。
横河計測株式会社
計測機器メーカーの横河計測株式会社は、自社サイトやYouTubeで 製品の使い方を解説するハウツー動画 を多数公開しています。
接続方法が複雑になっている製品ではアニメーションを使用して繋がっている部分をわかりやすく表現しています。注意点を記載することで、ユーザーの故障リスクやリスクエッジに繋がっています。
千代田精機株式会社
ガス圧力調整器や溶接機器を製造する千代田精機株式会社は、安全な使い方を示す動画マニュアルに注力しています。
「圧力調整器の取り付け方」では、音声なしでも理解できるようテロップ(字幕)を活用しつつ、重要なポイントや注意点を画面上に明示して、視聴者が危険なポイントを確実に把握できるよう工夫されています。高圧ガスは可燃性ガスなどの場合、爆発のリスクがあるためこういった動画マニュアルが特に重宝されます。
動画マニュアルを顧客に提供するメリット
視覚的にわかりやすく、安全性を確保
動画で実際の動作や正しい操作方法、注意すべき危険箇所を示すことで、ユーザーは直感的かつ理解しやすく製品を扱えるようになります。紙のマニュアルでは伝わりにくい微妙な動きも映像なら把握でき、誤った操作による事故を防止する効果が期待できます。
NG行為(やってはいけない使い方)を具体的に動画で見せることで、ユーザーに注意喚起し事故防止に直結させることができます。
問い合わせ・出張対応コストの削減
ユーザーが動画マニュアルを見て自力で問題を解決できる場面が増えれば、問い合わせ対応や出張サポートの回数を大幅に減らせます。実際、分かりやすい動画を提供することで カスタマーサービスへの問い合わせ対応リソースを削減し、ユーザー自身が疑問点を自己解決できるようになると指摘されています。メーカーにとってはサポート工数の削減につながり、結果的にコストダウンが期待できます。また、顧客側もすぐに解決策を得られるため満足度が向上します。
グローバル展開に強い
動画マニュアルは多言語対応が比較的容易で、海外ユーザーへの説明にも強みを発揮します。映像中心の説明は言語や文化の壁を越えて理解されやすく、仮に言語が異なっても視覚情報で補える部分が多いのです。さらに字幕やナレーション音声を差し替えるだけで別言語版を作れるため、複数市場に展開する際のコスト・時間を大幅に削減できます。文化的背景に合わせて内容をカスタマイズしやすい点もメリットで、各国のユーザーに適した形で正しい使い方を伝えることが可能になります。
田中科学機器製作会社では、日本語版と英語版の二つの動画を作ることで制作コストを抑えて自社製品をアピールしています。
動画マニュアルの企画ポイント
動画は短くセグメント化し、冗長にならないようにする
1つの動画が長すぎるとどこに必要な情報があるかユーザー側がわかりにくい可能性があります。対策として、1本の長い動画を作成して、それをセグメントごとにショート動画にすると顧客の利便性が増します。理想的には1本あたり1~3分程度に留め、内容ごとに区切って複数の短い動画に分けるのがおすすめです。重要ポイントを強調しつつ章立てすることで、視聴者は必要な情報だけを効率よく学べます。
テロップ(字幕や強調文字)の活用と適切な量
映像内で話している内容や注意点を補足するテロップは、重要ポイントの強調に有効です。ただし入れすぎると画面が情報過多になるため、強調したい箇所が埋もれないように注意しましょう。簡潔なキーワードや短いフレーズで要点だけ表示し、視聴の妨げにならないバランスを心がけます。
危険な作業にはNG例も盛り込む
映像内で話している内容や注意点を補足するテロップは、重要ポイントの強調に有効です。ただし入れすぎると画面が情報過多になるため、強調したい箇所が埋もれないように注意しましょう。簡潔なキーワードや短いフレーズで要点だけ表示し、視聴の妨げにならないバランスを心がけます。
動画マニュアル配布方法
せっかく作成した動画マニュアルも、ユーザーに届かなければ意味がありません。そこで、製造業メーカーが動画マニュアルを効果的にユーザーへ届けるための配布・共有方法を紹介します。
メールマーケティングでの活用
製品購入後のフォローアップメールに動画マニュアルへのリンクを盛り込む方法です。ユーザーが商品を受け取ったタイミングで、その使い方のコツやメンテナンス方法のヒントをまとめた「ハウツーメール」を送れば、顧客満足度の向上につながります。
例えば「商品は問題なくお使いいただけていますか?以下の動画で正しい使用方法をご確認いただけます」といった内容で案内すれば、ユーザーは困った際にすぐ動画を参照でき安心です。メールによる継続的な情報提供は、製品の活用促進だけでなく顧客との関係維持にも効果的です。
取扱説明書のPDFにリンクやQRコードを追加
従来の取扱説明書(紙やPDF)の中に、動画マニュアルへの導線を埋め込む方法です。具体的には、マニュアル内に動画URLを記載したりQRコードを掲載したりします。ユーザーはスマホでQRコードを読み取るだけで該当する動画を視聴でき、文章では分かりにくい部分も即座に理解できます。
YouTubeで公開
自社製品の動画マニュアルをYouTube上に公開しておけば、ユーザーは検索経由で容易に動画にたどり着けます。またYouTubeはスマホでもPCでも視聴しやすく、他者と共有もしやすい利点があります。注意点として、社内限定で公開したい内容の場合は限定公開設定や自社サイト埋め込みに留めるなどの工夫が必要です。
動画マニュアルの作成方法
絵コンテの作成の活用
どの製品のどの手順を動画化するかを決め、台本(シナリオ)や構成案を用意します。ユーザーがつまずきやすいポイントや重要な安全注意箇所を洗い出し、動画でどう見せるか計画しましょう。企画段階は動画制作の核となる部分で、制作会社に依頼する場合も最も工数と費用が掛かる工程です。
撮影(または画面録画)
実際の製品を使って操作手順を 撮影します。ハードウェア製品ならスマートフォンやデジタル一眼レフで現場の映像を撮ります。ソフトウェア製品の場合は画面操作をキャプチャ録画すると良いでしょう。撮影時のポイントとして、1つのシーンにつき引きの全体映像と、アップの詳細映像の2種類を撮っておくと分かりやすい映像になります。
例えば機械操作なら、全体の手順を映した映像と、手元の細かな操作を映した映像をそれぞれ撮影し、後で必要に応じて切り替えることで理解度が高まります。また、撮影中は製品マニュアルに載っている注意ラベルや安全装置なども映し込み、安全面の情報も盛り込むよう意識します。
動画編集
撮影した映像素材を編集ソフトで繋ぎ合わせ、不要な部分をカットします。基本的には時系列に沿って手順が分かるよう並べ、動きが飛びすぎないよう自然な繋ぎを心がけます。
ナレーション(音声解説)を入れる場合は、映像に合わせて 別途静かな環境で音声を録音し、後から挿入すると聞き取りやすい動画になります。工場など現場の騒音がある環境で撮影した場合、その場の音声は使わず後付けナレーションに差し替えることで、クリアな解説が可能です。必要に応じて社内の技術者やプロのナレーターに協力を仰ぐと良いでしょう。
また、自社に既存のイラストや図解資料があれば、そうした静止画素材を動画内に組み込むことで、一層わかりやすい映像に仕上がります。
動画マニュアルに関するQ&A
動画マニュアル制作の費用目安は?
制作費用は動画の内容や範囲によって大きく変動します。一般的には企画(台本作成)・撮影・編集の3工程それぞれにコストがかかり、実写でシンプルな内容なら 1本あたり数十万円程度からスタート可能です。
しかし、高度な 3DCGやアニメーションを取り入れると費用は増大し、例えば3D CG制作では5秒の映像で50万円前後かかるケースもあります。つまり、実写メインで簡易な編集なら比較的低コストに収まりますが、凝った表現を求めるほど費用は上がります。まずは必要最小限の内容で試作し、予算に応じてクオリティを上げていくのがおすすめです。
どのくらいの期間で作成できるの?
制作期間は動画の尺や内容の複雑さによって異なりますが、一般的な実写動画を制作会社に依頼した場合で およそ1~2か月が目安です。これは企画打ち合わせから撮影準備、撮影、編集、修正確認といった工程を経るためで、アニメーション動画でも同程度(1.5か月~2か月程度)が標準的とされています。もちろん、内容がシンプルで社内リソースも投入できれば 1か月未満で仕上げるケースもありますし、逆に複数言語展開や凝った編集を施す場合は3か月以上かかることもあります。製品リリース日が決まっている場合は、逆算して早めに着手することが重要です。
動画を更新した際、既存のリンクはどうしたらいい?
YouTubeでは一度アップロードした動画ファイルを同じURLのまま差し替えることはできません。そのため、印刷物やPDFに直接YouTube動画のURLやQRコードを載せてしまうと、動画内容の更新時にリンク切れや旧版参照のリスクが生じます。
対策として、自社サイト内に動画マニュアル専用ページを作成し、そこに動画を埋め込む方法がおすすめです。そのページのURLを取説や資料に掲載しておけば、動画を撮り直してもページ内の埋め込み動画を入れ替えるだけで済みます。ページURL自体は固定なので、印刷物を刷り直す必要もありません。一方、YouTubeに公開する場合は最新動画への誘導を工夫する必要があります。要はリンクが変わらない仕組みを自前で用意しておくことで、動画更新時の混乱を防げます。
まとめ
製造業メーカーにおける動画マニュアルの提供は、ユーザーの理解度向上と安全性確保、さらにはサポート効率化やグローバル対応力強化につながる有効な施策です。紙やPDFのマニュアルでは伝えきれなかった製品の使い方・魅力を、動画ならではのリッチな情報で補完でき、顧客満足度の向上と製品価値の訴求に寄与します。特に動きや音が重要な製品、安全注意が多い製品を扱うメーカーほど、その効果は大きいでしょう。
弊社では製造業1,000社のWebマーケティングを支援してきた実績があり、動画コンテンツの制作も可能です。製造業での動画制作に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。